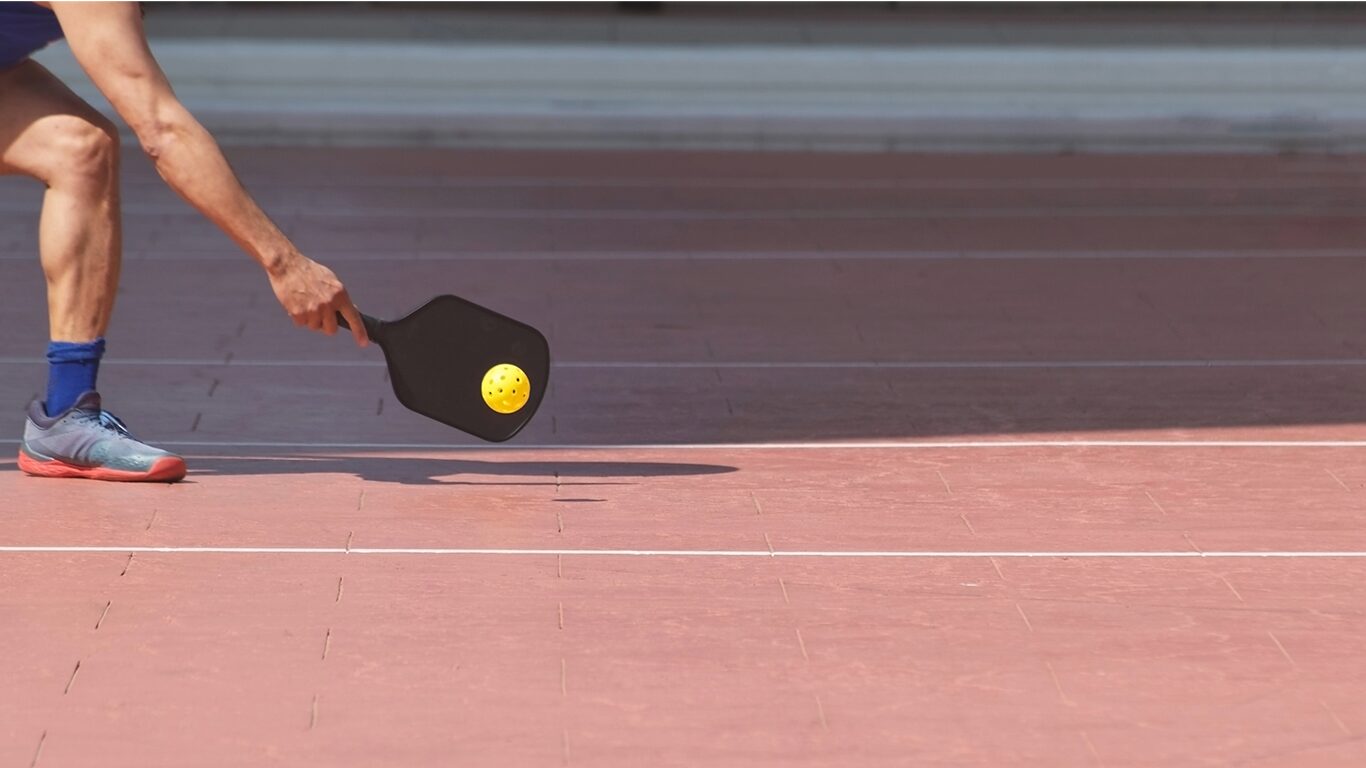フットフォルトを考える

フットフォルトを考える

ピックルボールにおける「フットフォルト」については、これまでに2度のルール改正が行われてきました。その背景や経緯を理解し、実際にフットフォルトが起きた(あるいは起きたと思われた)場面において、ルールに則った正しい判断ができるようになること。それが、今回の目的です。
フットフォルトとは?
フットフォルトとは、プレー中に選手の足や体の一部、あるいは身に付けている物が許されない場所に触れる/越えることで発生する反則です。
代表的なものは、
- サーブ時にベースラインを踏む、
- ノンボレーゾーン(キッチンライン)に足が入る、
といった例ですが、実際には以下のように多岐にわたります。
| フットフォルトの主な種類と具体例 |
| 【サービス時】 |
| ★ベースラインに触れる/越える → サーブの際、両足がベースラインの後方になければフォルト |
| ★サイドラインの延長線上より外側からサーブを打つ → サーブを打つ位置が、サイドラインの外に出てしまっている |
| 【ボレー時(ノンボレーゾーン関連)】 |
| ★キッチンライン(NVZライン)に足が触れる/越える → ボールをボレー(ノーバウンド)で打つ際、踏んでいた場合 |
| ★ボレー後の勢いでNVZ内に足が入る → 打った直後の慣性でラインを踏む、または踏み越える |
| ★帽子・サングラス・パドルなどがNVZ内に落ちる → 身体以外の持ち物がライン内に触れてもフットフォルトと見なされる |
| ★手やパドルでNVZに触れ、体を支える → 体勢維持のため、手やラケットで地面に触れると違反 |
| 【スマッシュやジャンプ後の着地時】 |
| ★キッチンに入った後、両足をつかず片足でジャンプ着地する → NVZ侵入後、正しく両足が設置されないままスマッシュなどを行うとフットフォルト |
ルール変更の変遷
フットフォルトに関する主なルール変更には、次のような変遷がありました。
2019→2020年 公平性向上のための見直し
2019年までは、審判がいない試合で相手からのフットフォルトの指摘があった場合、それを覆す手段がなく、そのままフォルトが認定されるケースが大半でした。
ルール「13.D.1.c」の項目です。
自分のコート側(非ボレーゾーン=NVZ やサービスフットフォルト)のフォルトは、自分またはパートナーが気づいた時点で即座に宣言すべきである
相手側のコートで発生したフォールト(NVZやサービスフットフォルト)についても、気づいた時点でコールすることが可能である
つまり、相手が「踏んだ」と言えば、それが通ってしまう唯一とも言えるケースでした。
例えば、11点ゲームの、9-10の相手マッチポイントでスマッシュ。10-10に追いついたと思いきや「フィニッシュ後、キッチンラインを踏んでいた」と相手チームから指摘を受けました。「どう見ても踏んでいない。相手は意図的にありもしないフットフォルトを捏造した」と思ったとしても、どうすることもできず、そのまま敗退となっていたのです。
これは「相手はウソをつかない」という性善説に基づいたルールだったのです。
それが2020年以降は、次のような項目が追加されました。
コールされたフットフォルトについてプレーヤー間で意見の相違が生じた場合、リプレーを行うものとする
選手間に互いに異議がある場合は、リプレー、やり直しとなるようルール改定。これにより公平性が強化されました。
2024→2025年 パートナー間の扱い明確化
このルール変更により、ダブルスの場合、コートにいる4人に判断が委ねられるようになりました。ただ2024年までは「Players」(プレーヤー間)で異議がある場合という表現で、パートナー間の不一致もリプレー対象に解釈される余地がありました。それが2025年には、「Teams」(チーム間)へと変更されたのです。
すなわちパートナー間の不一致はリプレー対象外になると明確化されました。
つまり、次のような例の場合です。
9-10の相手マッチポイントでスマッシュ。10-10に追いついたと思いきや、「フィニッシュ後、キッチンラインを踏んでいた」と相手チームから指摘が入りました。フォルト打ったとされる本人は「踏んでいない」と認めなかったが、その横にいた味方パートナーが「いや踏んでいた」と認めた。
この場合、やり直しではなく、「フォルト」を認め相手側のポイントになるということです。
また次のような文言に、「パートナー」も加わりました。
スポーツマンシップの精神に基づき、プレーヤー、またはパートナーは、いかなる種類のフォルトも、それが犯された、または発見された時点で、直ちに自分自身に宣告することが期待されます。フォルトの宣告は、次のサーブが行われる前に行われなければなりません
すなわち、本人が認めなくても、パートナーは味方に対して、即座にフォルトを宣告できると、明文化されたのです。
誠実な自己申告を
セルフジャッジの原則では、自陣のプレーについての判断は、自分たちで責任を持つのが基本です。
しかし、相手がルールを軽視している場合、それを指摘するのは難しく、プレッシャーのかかる場面では一層勇気がいります。
極端な例ですが、次のような「ルールの悪用」も理論上は可能です
例えば、11点ゲームの、9-10の相手マッチポイントでラインを踏んでスマッシュ。この土壇場で、相手が指摘するのは難しいだろうと、悪意を持ってキッチンラインに侵入していた。「フォルト」のコールを受けなければ、そのまま10-10。最悪コールを受けたとしても「絶対に踏んでいない」と主張すれば、リプレーになる、とルールを完全に悪用した場合です。
ただし、2025年からは「チーム間での意見の不一致」に限ってリプレーが適用されるため、チーム内での誠実な申告が非常に重要になっています。これにより、ルールの悪用リスクはかなり軽減されました。
いずれにしろ、こうなると、ラインジャッジで意図的にインをアウトとウソをつくのと同じ行為ですよね。これでは、セルフジャッジ自体が成り立たなくなってしまいます。
リクリエーションの意味合いもある楽しいピックルボールですが、ルールはルールです。「まあ、まあ、今日のところは、おまけでセーフということで」と言ってあげたいところですが、やはりフォルトはフォルト、です。

このノンボレーゾーンの、わずか数センチの差が、ピックルボールをより面白みあるものにしていることは、みなさんが一番よくご存知なのではないでしょうか。
気持ちよく「踏みました!」と自分で宣言してもらうのが、やっぱり最良の解決策です。
「たかが数センチ、されど数センチ」。
正しいルールの理解と、誠実な自己申告が、ピックルボールの醍醐味を守ると言えそうですね。